旅館には絶対に戻りたくなかった――そう語るのは「季譜の里」の4代目。多様なカルチャーとのふれ合いから生まれた彼の想い、そして目指す未来をひもときます。
ゲスト
株式会社季譜の里 代表取締役社長
佐々木 慎太郎
1976年、岡山県出身。湯郷温泉・季譜の里 4代目として、代表取締役社長を務める。大学卒業後、2年間の海外旅行を経験。帰国後、東京の出版社に勤務したのち岡山県へ戻り、家業である季譜の里を継ぎ現職。
インタビュアー
株式会社 Loco Partners 代表取締役副社長
塩川 一樹
1979年生まれ、立命館大学経済学部卒。株式会社ジェイティービーを経て、株式会社リクルートへ中途入社。旅行事業部にて、首都圏・伊豆・信州エリア責任者を歴任し約2,000施設以上を担当。2012年7月より株式会社Loco Partners取締役に就任。
第1章 バンド、映画、そして旅に明け暮れた青春時代

塩川:佐々木さんの幼心には、どんな「宿の発祥の記憶」があるのでしょうか。
佐々木:この宿の前身は、湯郷温泉の「たけのや」という宿で、私の曾祖父母が昭和8年にはじめました。それから昭和48年に場所をここへ移転してできたのが「湯郷プラザホテル」。湯郷温泉で最初の「靴で上がれる旅館」で、当時の湯郷では珍しいホテル形式の旅館でした。私が生まれたのはその3年後の昭和51年。今の、季譜の里ができたのは平成14年です。
塩川:ご長男として誕生されたと伺っています。どのような幼少時代を過ごされたのですか。
佐々木:子どものときには宿の中を走り回ってかくれんぼをしたり、売店のジュースを飲んだり、土産もののきびだんごを食べたりしていましたね。中学生、高校生になってからはバンドを組んで音楽をしていました。
塩川:宿の中が遊び場という幼少時代を過ごされ、中学、高校時代は仲間とバンドに熱中されたのですね。中学3年生で一人暮らしをはじめられたとも伺っています。当時は、自炊などもされていたのでしょうか。
佐々木:はい。中学校3年生になり、絵を描きたいという理由から寮を出て一人暮らしをはじめたのです。小学生のときから父親も母親も仕事に出ていて家にいなかったので、料理を自分でつくって食べるということは、もともと自然にこなしていましたね。
塩川:たくましさを幼少期に身に着けていたわけですね。そうして中学から高校時代をすごされて、先の進路はどのように考えられたのでしょうか。
佐々木:バンドをしていたこともありまして、東京に行って音楽をしたかったのです。そこで、青山学院大学の第二経済学部に進学しました。そして大学でまたバンドをやろうと思っていたのですが、メンバーが見つからず映画研究会に入りました。高校のときから曲の詞や本を書いたりするのが好きで、同じように映画も好きでした。
塩川:クリエイティブな青年時代ですね。音楽は断念しても、佐々木さんの中ではなにかを生み出したいという気持ちは変わらずにあって、そこにのめり込んだ4年間だったのでしょうか。
佐々木:そうですね。映画研究会で映画を撮影するのですが、脚本を私が、カメラが好きな人がカメラマンを担当して映画を撮影していました。上映会があれば場所を借りて、告知のチラシをまいたり、企業に協賛をお願いしたり、4名ほどのメンバーで一生懸命やりましたね。ですが、先輩方が卒業されてからは映画研究会よりも海外旅行に夢中になりました。
塩川:興味の対象が、海外という広いフィールドに移り変わっていったのですね。

佐々木:映画や小説の影響で、自らその場所に行きたいと思いました。最初はアメリカ、次にメキシコ。そこで今の妻に出会いました。それが大学3年生の春休みで、卒業後にタイ、インド、ネパール、スペイン、モロッコなど33カ国を2年間かけてまわりました。
塩川:旅行から戻られて、「帰国後はいつか自分が実家の旅館を継ぐのだ」という気持ちはおありでしたか。
佐々木:旅館には絶対に戻らないという逆の気持ちがあり、東京の出版社に入社しました。親が敷いたレールの上を歩きたくないという気持ちがあったのだと思います。フリーランスになるための修行だと思い3年間勤めたのですが、実はその後、独立に失敗してしまったのです。そのためアルバイトをはじめたのですが、半年ほど経って、学生時代に行けなかったインド北部へ旅に出ました。実家に連絡を入れずにインドへ行っていたのですが、日本に戻り妻(当時の彼女)の家に帰ると、「母親が心配しているから電話するように」と言われ、実家に電話するとすぐに実家に戻るよう母に促されました。
第2章 「自分の道」との出会い、「花のもてなし」への気づき
塩川:久しぶりにご実家に戻られたのですね。それはおいくつの頃だったのでしょうか。
佐々木:28歳ですね。当時は実家に立ち寄っただけ、というくらいの気持ちで、旅館を継ぐ気はなかったのですが、帰ったらいきなり「働きなさい」ということで、2日目にはもう働かされていました。私が戻った頃というのは、折しも旅館を改装して3年目、団体旅行から個人旅行へ移行していく変化のタイミングだったのですね。当時は、インターネットでの集客を得意とする旅館はまだ存在しませんでした。しかし、私は小説や映画の脚本を書いた経験があったからか集客の広告を作るようなことが得意で、実家に戻ってから5年ほどで社長に就任することになったのです。その頃には、「やりたくない」という気持ちが「俺がやるのだ」という気持ちになっていました。

塩川:時代の変化に合わせて宿も変化していかなければ、という風潮が感じられるようになってきた頃でしょうか。宿泊の販売方法やお客様の環境が変化する、激動の期間だったと思いますが、その中にどんな面白さがありましたか。
佐々木: 面白いのは「顧客の満足」ですね。小説を書いていて一番難しかったのは、数人に読んでもらい感想もらうまで、自分が書いている内容の良し悪しがわからないことでした。それに比べて、バンドは目の前のお客様の反応なのでとても分かり易かった。旅館での顧客満足の追求で得られる満足感は、自分が世の中に価値を生み出しているというという感覚と直結します。
塩川:お客さまは、滞在中にどんなことを思うのだろうと想像するのですね。そうしたことを通して、佐々木さんの立ち位置は「旅館業に魅せられている状態」に変化されたと。自分の道はここなのだということが見えてきた30代前半だったのですね。ところで今回、季譜の里にお邪魔してもっとも印象的なのが、自然やお花です。どんなこだわりがあるのでしょうか。


佐々木:祖母の名前が「菊野」だったことが関係あるかどうか分からないですけれども、祖父は菊の花をたくさん育てていました。季譜の里の前身の「湯郷プラザホテル」がある湯郷中に花を配って、湯郷の街中を花で飾ろうとしていました。また、祖母も母も生け花を嗜んでいたこともあり、季譜の里が栄えているのは花を大事にしているからではないかという思いが出てきたのです。
塩川:それが、いわば現在の季譜の里の「原点」なのですね。
佐々木:季譜の里のコンセプトは「花」で、女将がこのような野の花が咲きみだれる庭を好んでいるのです。季譜の里には純和風の庭もあるのですが、以前、その純和風の庭にたんぽぽが咲いたことがありました。たんぽぽは雑草ですし、「この宿と庭にはそぐわない」と女将に相談しましたら、女将は「これはこのままにしておく方が良い」と言いました。この感覚がうちの宿の良さなのであって、キリッとした中にも親しみがわいてくるような、柔らかさが残るような旅館をつくっていけばいいのだなと、そのときに思いました。
塩川:花のあり方を説かれて宿のあり方を知る、ですね。季譜の里は、上質だけれども緊張感があるわけではなく、着飾らないありのままの様子にあたたかみを感じられるのですが、まさにそこが原点なのだと改めて知ることができました。

第3章 インバウンドへの挑戦と未来のコミュニティの創造
塩川:海外を旅されて感じられた、日本旅館の魅力についてお聞かせください。


佐々木:海外からみた日本旅館の良さは、ありきたりではありますが、浴衣で過ごせることですね。ホテルならスーツでレストランに行きますが、旅館は違います。そうした空間は、海外にあまりないのではないかと思いますね。
塩川:食事会場は本来であればオンタイムの場ですが、旅館ではまるでオフタイムのようにドレスダウンが許されるので気持ちも解きほぐされます。リラックスできる場所を提供する、特別な空間だと感じますね。海外といえば、季譜の里ではインバウンドの旅行会社を立ち上げられたと伺っています。その背景もお聞かせください。
佐々木:一番の理由は、交通の便の悪さです。季譜の里単体では、お客さまに足を運んでいただけないということですね。国内のお客さまであれば、自家用車やレンタカーでお越しいただけます。しかし、海外からのお客さまはほとんど電車でいらっしゃいますから、車が必要な季譜の里まではお越しいただけない。そこで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R)や姫路城など、近隣のレジャーとセットのツアーとして売りだすことで季譜の里にお越しいただくのです。
塩川:エリアの魅力を活用しながら、お客さまの開拓を自らおこなうということですね。
佐々木:そうですね。やはり、セグメントは小さくして一人ひとりのお客さまに楽しんでいただけるものにしなければ、とは思っています。しかし、旅館はお客さまをお受け入れできるキャパシティが決まっている一方で、旅行会社はそうではありませんから、インバウンドではあえて近ごろ成長著しい国をターゲットにしているのです。インバウンドで最初の成功の実感をつかむまでのターゲットは、タイの方々です。
塩川:最後に、季譜の里としての未来への展望をお聞かせください。
佐々木:この先、人口が減少することだけは数字で分かっておりますので、まずは人が減って行く中でどうやって田舎を活かしていくか。そして、各地方が自ら責任をもって自主的に地方創生を推進していかなければいけませんね。その中で、兵庫県の城崎や熊本の黒川などは本当に優秀で、一致団結してその地域の特色を出しています。そのように、地域がひとつになって特色を出していくことを、みんなが本気でやらなければならないと思います。
塩川:そうなると宿だけではなくて、周囲との協力や新しいことにチャレンジするという視点が大切になってきますね。

佐々木:まさに、それがとても大切になると思います。しかし、周囲との協力が叶わなくとも、旅館単体でもいいと思っています。地域でも旅館でも、人が集まりたくなる環境づくりこそが活性化の始まりで、これからの田舎には理想的なライフスタイルが求められます。理想的なライフスタイルとは「一人ひとりが輝ける社会がそこにあること」であり、大切なのは「いつまでもその土地で安心して暮らしていけると思えること」です。それは土地への執着ではなく、愛情のようなものですね。それを、まず季譜の里からつくりはじめると。そして、今は、同じ価値観の人と簡単につながることができる時代になりました。地域だけにコミュニティが存在する時代ではありません。また、文化も都会だけで出来あがっていく時代ではありません。ネットのような仮想世界でも、文化はどんどん膨らんでいます。季譜の里の価値観は、お客さまだけでなく、野菜を作る農家の方、酪農家の方、水産業の方、同じ価値観を持つ人間同士がつながり、ひとつのスタイルの世界をつくりあげるということです。つまり、旅館は大きな世界の一角と言えるのかもしれません。これから、観光業の時代が来ます。地域という横のつながり、価値観という縦のつながりの両方を大切にして、日本の素晴らしさを世界に発信していたらと思っています。
塩川:佐々木さんが先々代や先代から継承したものが巡っていく様子、そして人との関わり合い、コンセプト。そういうものを大切にした宿だということを、改めて認識できました。本日はありがとうございました。
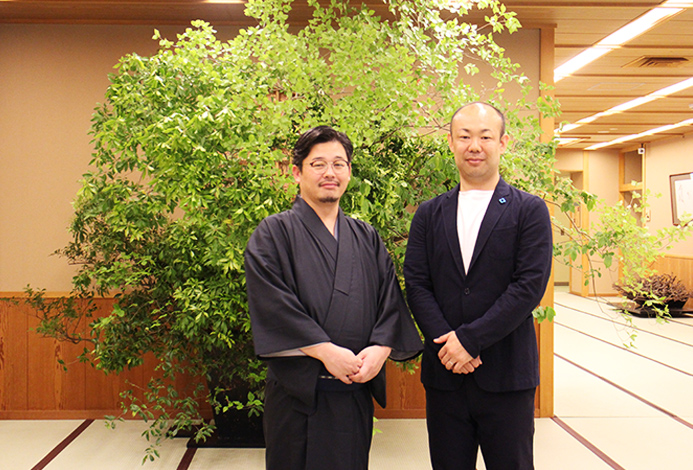
写真:杉原 恵美 / 文:宮本 とも子
株式会社季譜の里 代表取締役社長
佐々木 慎太郎
1976年、岡山県出身。湯郷温泉の老舗旅館「季譜の里」4代目として、代表取締役社長を務める。大学卒業後、2年間の海外旅行を経験。帰国後、東京の出版社に勤務したのち岡山県へ戻り、家業である季譜の里を継ぎ現職。













